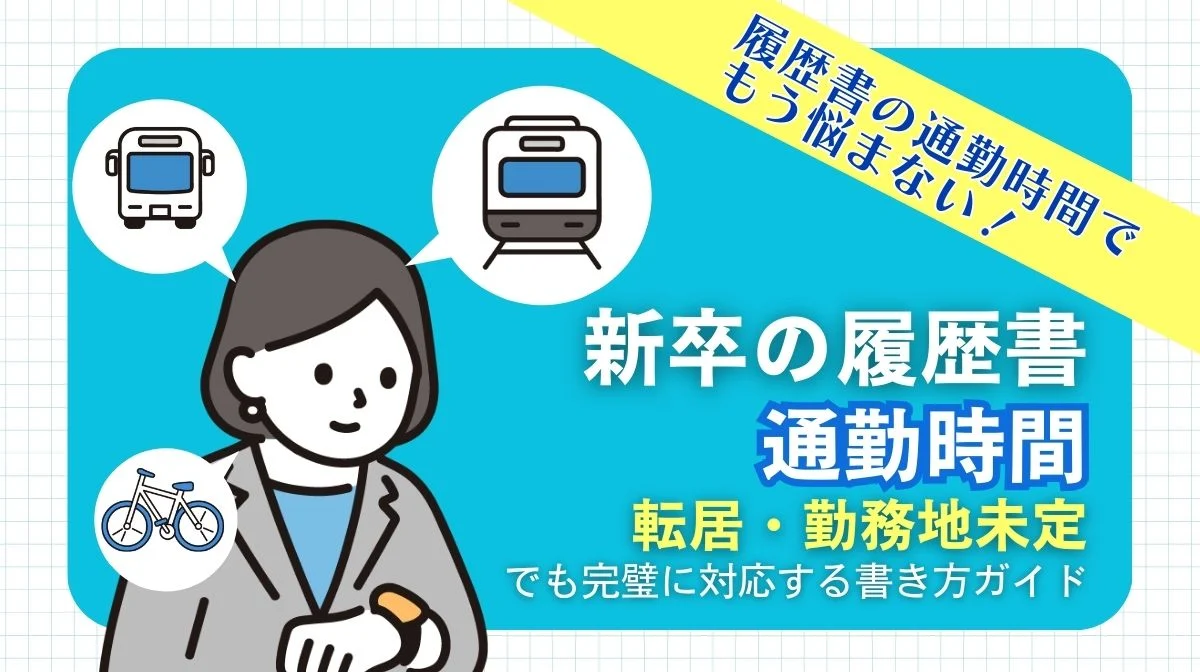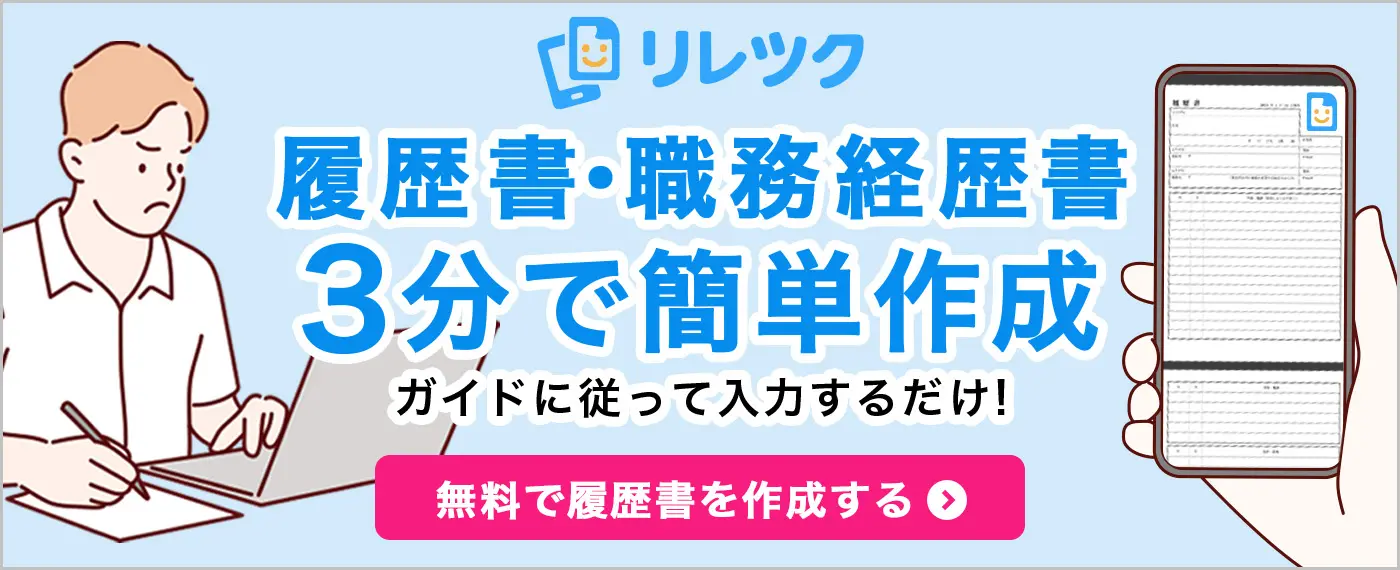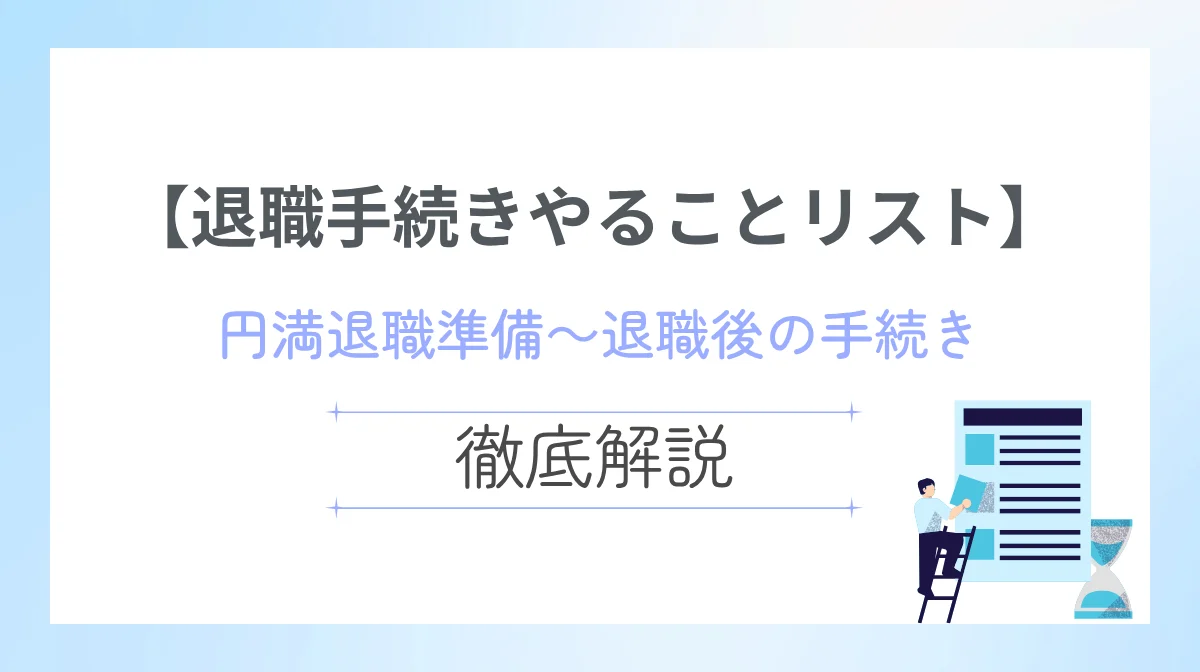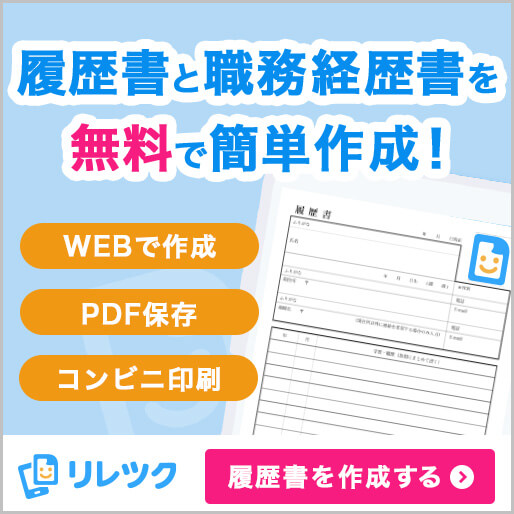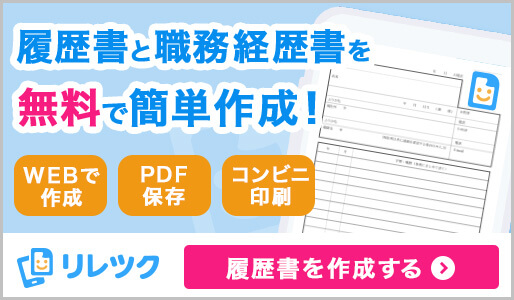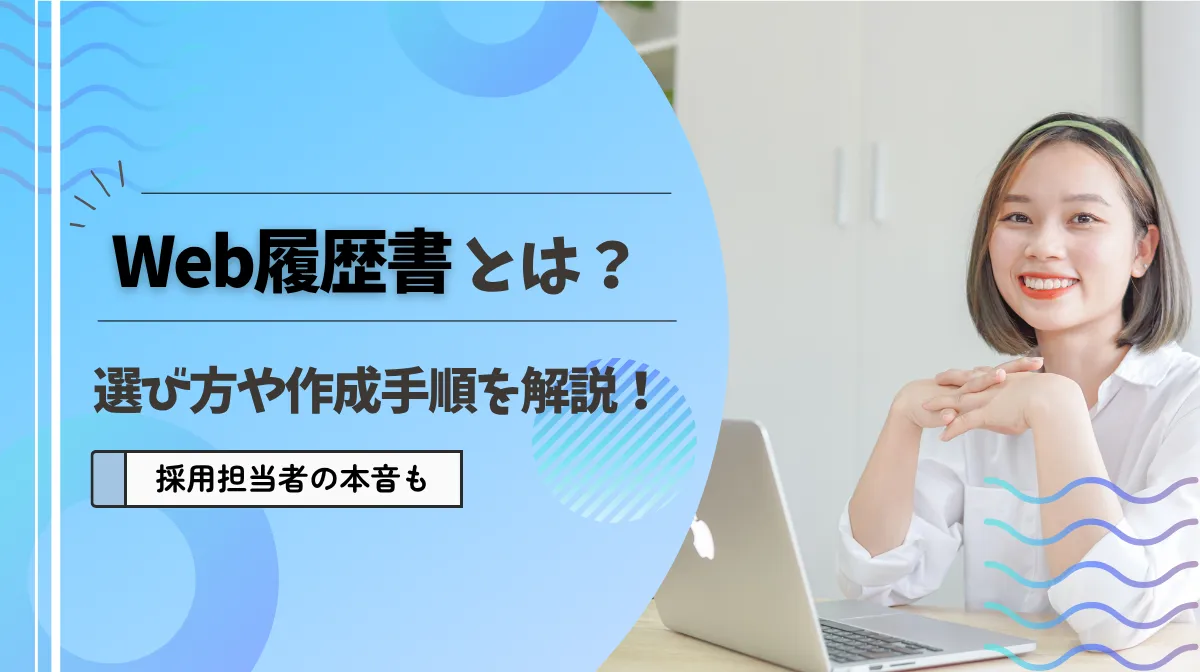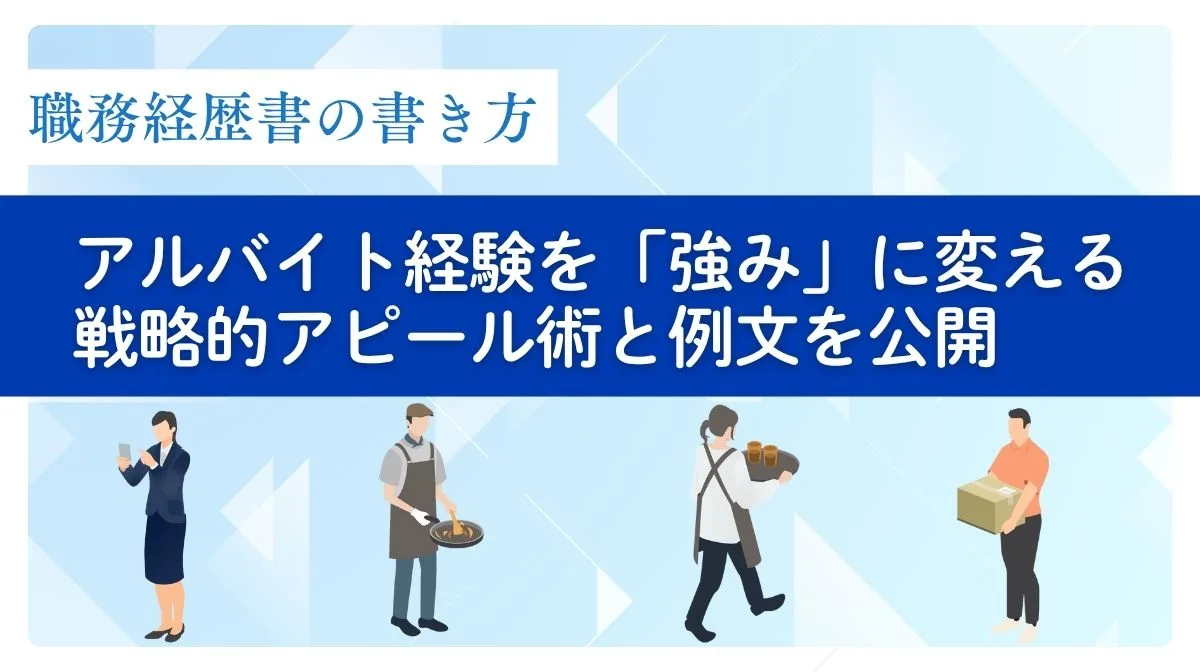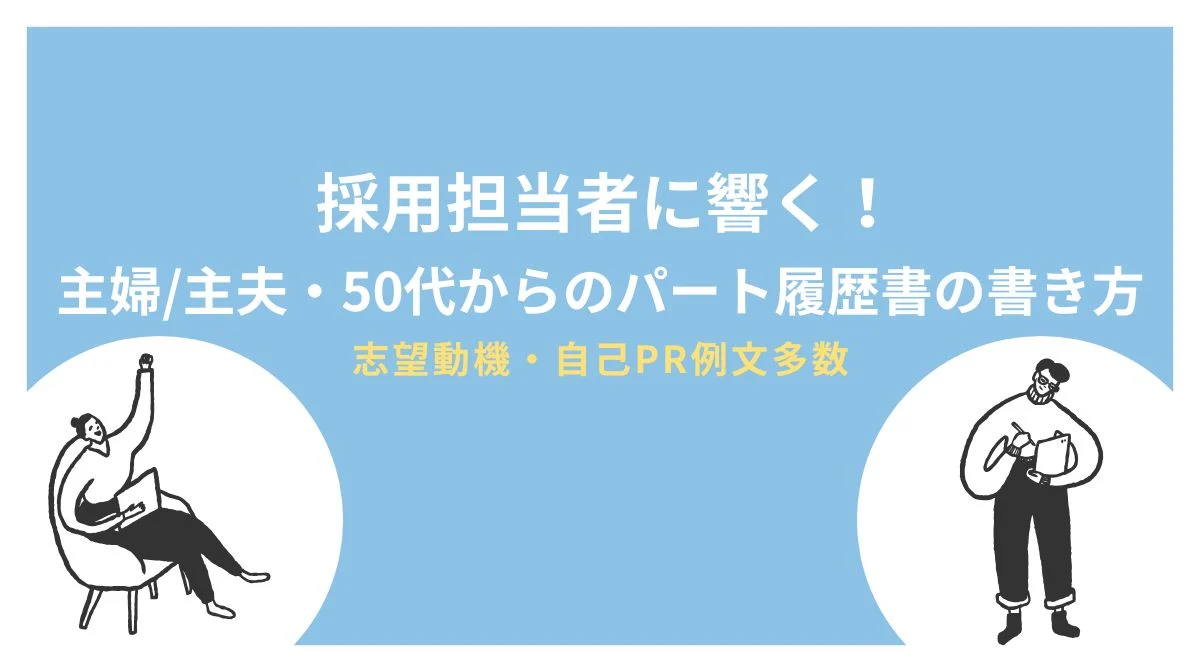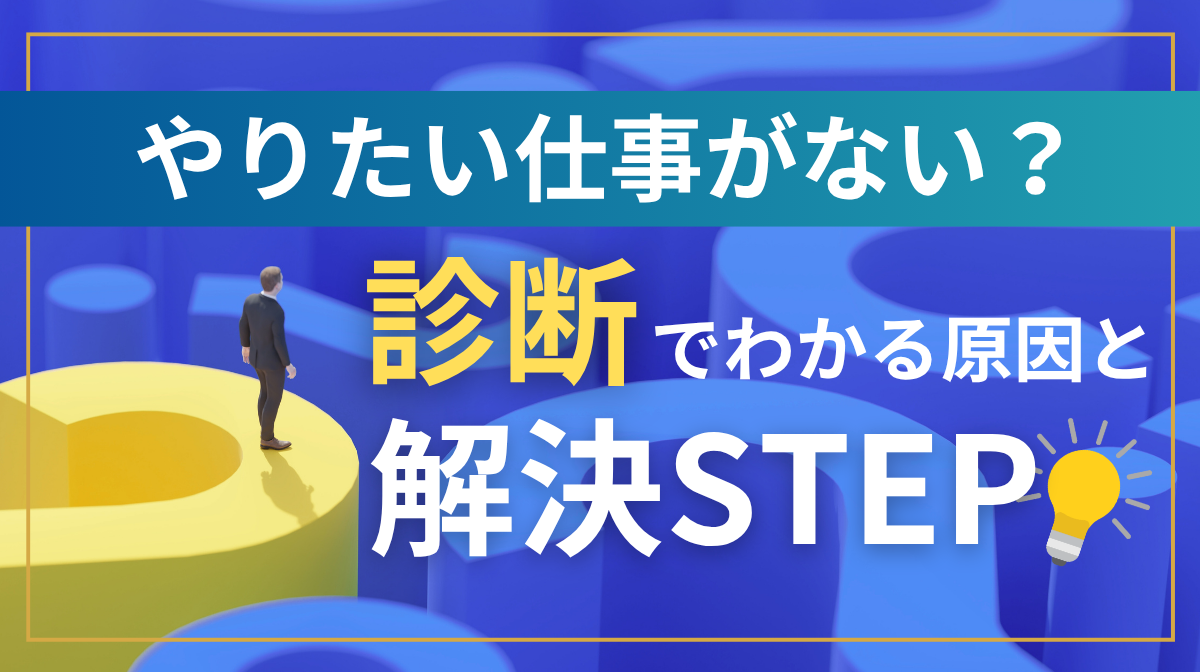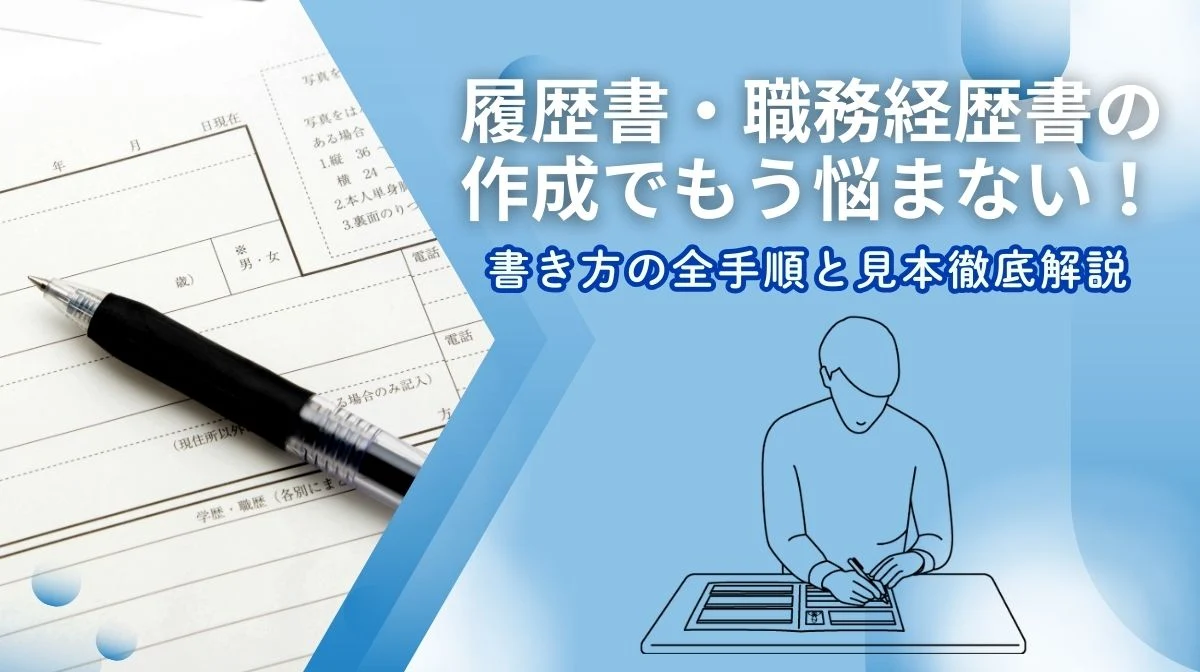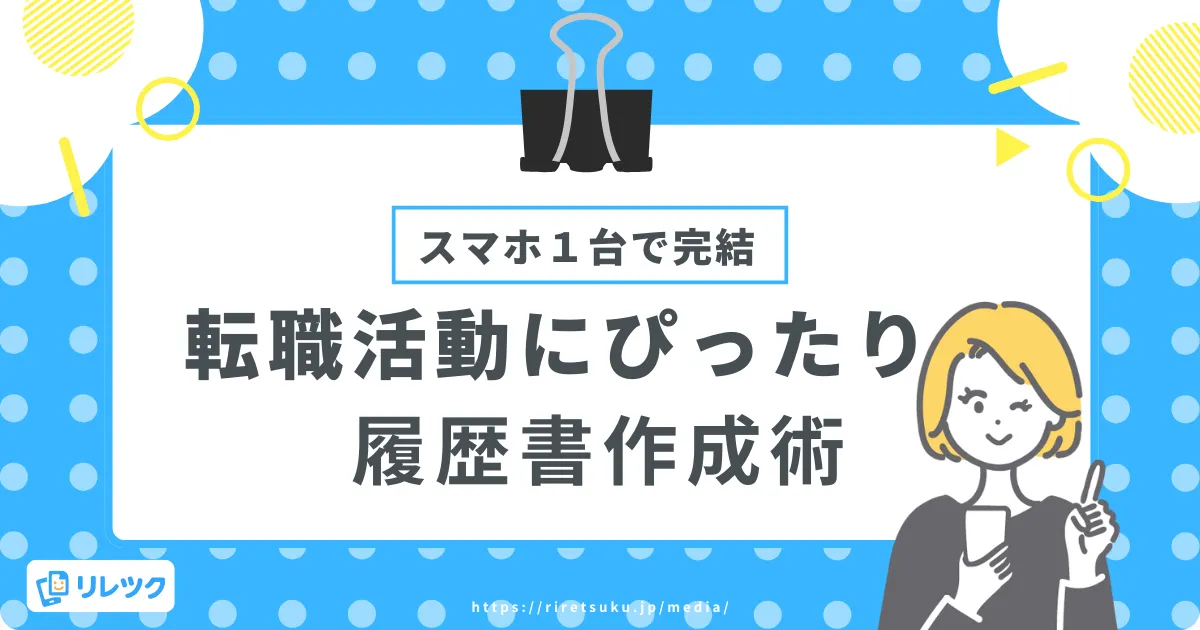新卒の就職活動で多くの人が悩む、履歴書の「通勤時間」欄。特に、まだ住む場所が決まっていない場合、「どう書けばいいのかわからない」と不安に感じてしまうのは当然のことです。
この記事では、通勤時間の基本的な書き方から、転居予定や勤務地未定といった「わからない」状況に対応するための具体的な記入例まで、あらゆる疑問を解決します。
1.実は必須ではない?厚生労働省が履歴書から「通勤時間」欄を削除した本当の理由

「通勤時間欄は必ず埋めなければならない」と思っている方も多いかもしれません。しかし、厚生労働省が2021年に公開した新しい履歴書の様式例では、「通勤時間」の欄そのものが削除されています。
これは、応募者の能力や適性とは関係のない情報で選考に不利益が生じないように、という配慮からです。
とはいえ、多くの企業では依然として従来のフォーマットが使われており、通勤時間の記入が求められるのが実情です。空欄は意欲がないと見なされる可能性もあるため、求められている場合は適切に記入する必要があります。
まずはこの背景を知ることで、「書けない」というプレッシャーを少し和らげましょう。
- 履歴書の通勤時間欄の基本的な書き方と計算方法
自宅から会社までのドア to ドアの片道時間を、5分単位で丸めて記入する具体的なルールと、地図アプリを使った正確な算出方法がわかります。 - 転居予定や勤務地未定など「わからない」状況での対処法
住む場所が決まっていない新卒者向けに、確実度別の例文や勤務地未定・リモートワーク希望時の具体的な記入方法がわかります。 - 通勤時間に関する企業の視点と全国平均データ
なぜ企業が通勤時間を重視するのか、平均40分・限界90分というデータと、長時間通勤時の懸念払拭方法がわかります。
2.そもそも履歴書の「通勤時間」とは?定義と3つの基本原則

通勤時間を正しく記入するためには、まずその定義を正確に理解しておくことが大切です。
一般的なビジネスシーンでは、以下の3つの原則に基づいて計算します。
通勤時間とは?3つの基本原則
原則1:ドア to ドア・片道
自宅の玄関から会社の入口まで、徒歩や待ち時間も全て含めた片道の時間を記入します。
原則2:最短の合理的経路
新幹線や特急など、特別な追加料金が不要なルートの中から最短時間を選びます。
原則3:正確な計算
地図アプリなどを使い、実際の通勤ラッシュの時間帯で検索するのが正確です。
原則1:自宅から会社までの「ドアtoドア・片道」の時間
履歴書に書く通勤時間とは、自宅の玄関を出てからオフィスのドアに着くまでの、片道の所要時間を指します。
家から駅までの徒歩時間、電車の待ち時間、駅からオフィスまでの徒歩時間など、すべての移動時間を含めて計算するのが基本です。
原則2:特急などを使わない「最短の合理的経路」を選ぶ
新幹線や特急のような特別な料金が必要な交通手段は、毎日使うことが現実的でないため、通勤経路には含めないのが一般的です。
企業側も、社員が日常的に特急料金を負担することは想定していません。
追加料金のかからない普通電車や快速電車、バスなどを利用した最も早く着くルートを「合理的経路」として選択してください。
ただし、グリーン車などの座席指定料金も同様に除外して考えるのが適切です。
原則3:Googleマップ等を使った正確な計算方法と注意点
通勤時間の算出には、「Googleマップ」や「Yahoo!乗換案内」などの地図アプリや乗り換え案内アプリを利用するのが最も正確で便利です。
利用する際は、実際の通勤時間帯(朝のラッシュ時など)の出発時刻で検索するのがポイントです。
日中の空いている時間帯で検索すると、実際とかけ離れた時間になってしまう可能性があるため注意しましょう。
3.採用担当者に伝わる完璧な記入フォーマット:4つの基本ルール

時間を計算できたら、次は履歴書に書き込む際のルールです。採用担当者が読みやすく、誤解のないように、以下の4つのルールを守って記入しましょう。
採用担当者に伝わる4つの記入ルール
5分単位で丸める
例:「32分」→「30分」、「48分」→「50分」
「0時間」と書く
例:「45分」→「0時間45分」
交通手段を補足する
例:「(電車、バス利用)」
空欄は絶対に避ける
意欲がないと見なされる可能性も。
▼あわせて読みたい
通勤時間の書き方だけでなく、履歴書全体の基本的なルールやマナーに不安はありませんか?採用担当者に好印象を与えるフォーマットや、学歴・職歴、自己PRなど各項目のポイントを網羅的に解説したこちらの記事の完全ガイドもぜひご覧ください。
4.【状況別】「通勤時間がわからない」を解決する究極の書き方ガイド

ここからは、新卒の就職活動で最も多い「通勤時間がわからない」という悩みを解決するための具体的な書き方を、状況別に解説します。
「わからない」を解決!状況別書き方ガイド
ケース1:転居予定の場合
採用後に引っ越す意思があることを誠実に伝えます。確実度に応じて書き分けましょう。
ケース2:勤務地が未定の場合
本社や主要な事業所など、最も可能性の高い勤務地を基準に算出し、その旨を補足します。
ケース3:リモート希望の場合
研修や会議での出社を想定し、本社までの時間を記載。希望も併記するのが丁寧です。
ケース4:通勤経路が複数ある場合
複数の路線や交通手段が考えられる場合は、追加料金のかからない最も合理的で早いルートを一つ選んで記入します。
ケース1:転居予定・可能性がある場合(確実度別の例文3選)
実家から通えない、あるいは一人暮らしを始める予定があるなど、転居を伴う場合は、その確実度に応じて書き方を変えるのがポイントです。
ケース1例文
【確実性が低い場合】
まだ具体的な転居先は決めていないものの、採用されたら引っ越す意思がある場合の書き方です。
(記入例)採用いただけましたら、貴社規定に従い、通勤可能な範囲へ転居を予定しております。
【ある程度具体的な場合】
住みたいエリアの目星がついているなど、ある程度計画が進んでいる場合の書き方です。
(記入例)現時点では未定ですが、採用後は〇〇線沿線(通勤30分圏内)に転居を予定しております。
【新居が確定済みの場合】
すでに入居する物件が決まっている場合の書き方です。
(記入例)約 0 時間 25 分(〇月〇日転居予定の新住所より算出)
ケース2:勤務地が未定・複数ある場合(例文あり)
総合職などで、配属先が採用後に決まる場合の書き方です。
この場合は、本社や主要な事業所など、最も可能性の高い勤務地を基準に時間を算出し、その旨を補足します。
複数の事業所がある企業では、新入社員は本社での研修から始まることが多いため、本社を基準にするのが無難です。
また、事前に企業の採用ページや説明会で配属の傾向を調べ、最も現実的な勤務地を選択することで、より適切な通勤時間を記載できます。
(記入例)約 1 時間 05 分(本社配属の場合)
ケース3:リモートワーク・在宅勤務を希望する場合
リモートワークが主体の企業に応募する場合でも、通勤時間の記入は必要です。
研修期間中の出社や、定期的な会議、チームミーティングなどで出社する機会が想定されるため、本社までの時間を記載するのが一般的です。
完全在宅勤務の企業であっても、緊急時の対応や重要なプレゼンテーション、年次総会などで出社を求められる可能性があります。
そのため、実際の通勤時間を正確に算出し、リモートワーク希望の旨も併記することで、企業側に配慮と準備があることを示せます。
(記入例)約 1 時間 10 分(本社所在地を基に算出。貴社規定のリモートワーク制度の活用を希望します)
ケース4:通勤経路が複数考えられる場合
複数の路線や交通手段が考えられる場合は、原則2で解説した通り、最も合理的で時間のかからないルートを一つ選んで記入します。複数の経路を記入する必要はありません。
▼あわせて読みたい
転居や勤務地などの状況を伝える際、自己PRの書き方も重要です。新卒の就活でライバルと差がつく自己PRの考え方から、具体的な構成、文字数別の例文まで徹底解説。あなたの魅力を最大限にアピールする方法を確認しましょう。
5.私の通勤時間は長い?データで見る全国平均と許容範囲

「この通勤時間だと、選考で不利になるのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。
客観的なデータと比較して、自身の状況を把握してみましょう。
調査データが示す「理想の通勤時間」と「限界ライン」
データで見る通勤時間
一般的に、企業は1時間30分を超えると心身への負担を懸念する傾向があります。
もし平均より長くても、「本人希望欄」で体力や自己管理能力をアピールすることで、企業の懸念を払拭できます。
総務省統計局の調査によると、全国の通勤時間の平均は片道あたり約40分です。
また、株式会社学情が20代を対象に行った調査では、「15分~30分」を希望する声が最も多いという結果も出ています。
一般的に、企業側は通勤時間が1時間30分を超えると、従業員の心身への負担が大きく、長期的な勤務が難しいのではないかと懸念する傾向があるようです。
参考:
ニッセイ基礎研究所 都道府県別平均通勤時間
HRog 20代の32.1%が「希望の通勤時間は15分~30分」と回答、株式会社学情調査
通勤時間が長い場合の懸念を払拭する本人希望欄の書き方
もし自身の通勤時間が平均より長い場合でも、伝え方次第で企業の懸念を払拭できます。
履歴書の「本人希望記入欄」などを活用し、通勤に対する前向きな姿勢や体力があることを補足しましょう。
(記入例)
大学へも片道約1時間30分かけて通学しておりましたが、4年間無遅刻無欠席で学業に励みました。体力には自信があり、通勤時間を有効に活用したいと考えております。
6.なぜ企業は今でも通勤時間を尋ねるのか?採用担当者の2つの視点

厚生労働省が必須項目から外したにもかかわらず、なぜ多くの企業は通勤時間を知りたがるのでしょうか。
主に2つの理由があります。
応募者の健康維持と長期的な就労継続性を配慮
長時間の通勤は、知らず知らずのうちに心身の疲労を蓄積させ、仕事のパフォーマンス低下や早期離職につながるリスクがあります。企業は、応募者が無理なく働き続けられる環境かどうかを判断する材料の一つとして、通勤時間を見ています。
交通費というコストを算出するため
多くの企業は通勤手当を支給しており、その上限額は企業によって様々です。事前に大まかなコストを把握する目的もあります。
7.不確実な状況を、プロフェッショナルな自己PRに変えるために
履歴書の通勤時間欄は、新卒の就活生にとって悩ましい項目の一つです。
しかし、その背景にある企業の意図を理解し、自身の状況に合わせて誠実に記入することで、「わからない」という不確実な状況を、むしろ計画性や入社意欲をアピールするチャンスに変えることができます。
今回紹介した書き方や例文を参考に、自信を持って履歴書を完成させてください。